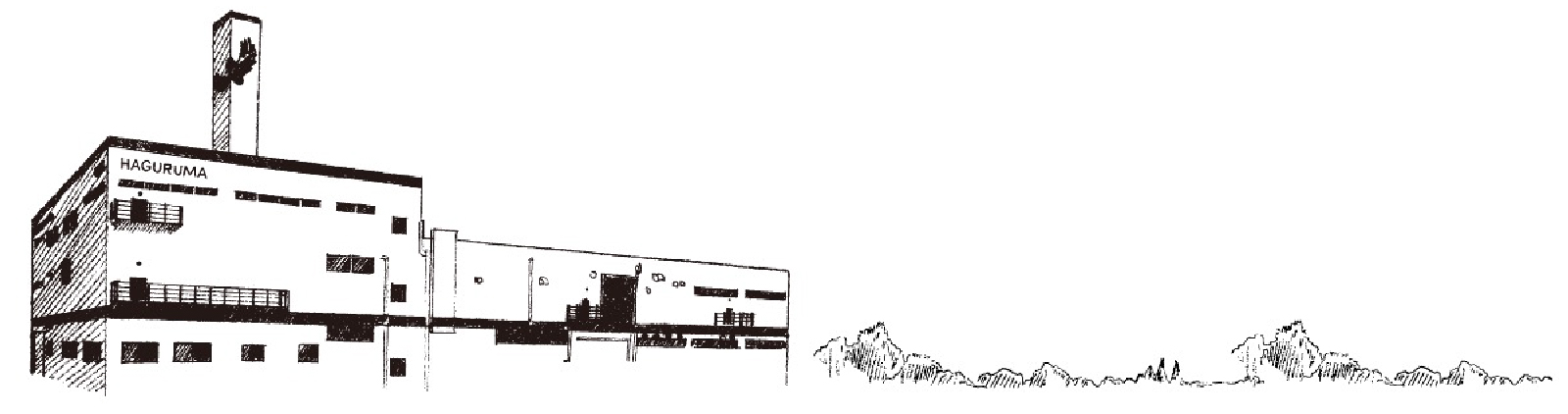コラム「紙と生活」
その紙が私たちのライフスタイルの中でどのような存在なのか、また今後どのようになっていくのかをトレンドやデータを元に様々な視点で考察するコラムです。
-

牛乳パック、デザインの秘密(後編)
2015/06/30

牛乳パックの上部に、半円状の切り込みがあることをご存知でしょうか?何気なく毎日見ているものの、その意味について知っている方は少ないのでは、と思います。 実はこの切り込みは、目の不自由な人に対する目印なのです。 1995年に食品団体が行った調査で、視覚障がい者やお年寄りが紙パック飲料の違いを見分けにくいということがわかり、とりいれられたアイディア。 現在では、国内で生産されるほぼ全ての牛乳パック(成分無調整牛乳に限る)に切り込みを見ることができます。
-

おいしさ届ける牛乳パック、100年の歴史(前編)
2015/05/27

人間が牛を家畜とし、搾乳をはじめたのは中東地域が最初だと言われています。およそ八五○○年前のことです。 牧畜が発展するのに伴い、牛乳を飲用するという習慣も世界中に広がっていきます。 街中に牛乳屋が登場したのは15世紀のロンドンのこと、そしてアメリカでも17世紀ごろには牛乳販売が行われていたという記録が残っています。
-

紙幣の原料とリサイクル(後編)
2015/05/01

紙幣の歴史について、さらには特殊な印刷技術について学んできましたが、今回は使われている原料についても調べていきましょう。 日本の紙幣は、みつまた(三椏)やマニラ麻を混ぜ、専用の特殊な用紙をつくっています。三椏は日本で古くから和紙の原料として使われてきた植物。 ジンチョウゲ科の落葉低木で、皮から繊維をとって和紙にします。 マニラ麻とはバショウ科の植物でフィリピンなどの熱帯で栽培されています。 約7メートルにも及ぶ背の高さで、バナナの木に似た姿。 特徴はなんといっても軽く丈夫なこと。 さらに耐水性もあるので、船でつかうロープの原料としても愛されています。
-

紙幣に隠された7つのスゴイ技術(中編)
2015/04/06

日本銀行が正式に紙幣を発行したのは、1885年のことです。 最初のお札は十円札でした。デザイナーはイタリア人のエドアルド・キヨッソーネ。 彼は印刷屋の家系に生まれ育った版画家で、技術を日本人に伝えるために大隈重信が呼び寄せました。 キヨッソーネは十円札の発行後も日本に永住し、紙幣や切手など500点余りを制作、亡くなるまで日本の印刷史に大きく尽力しました。 余談ですが、教科書でおなじみの西郷清盛の肖像画もキヨッソーネの手によるものなんだとか。
-

物々交換からうまれた紙幣の歴史(前編)
2015/03/20

紙幣の歴史の前に、お金がどのように生まれたのか簡単に触れておきましょう。 お金という物が存在しなかった古代では、人々は互いに物を交換することで、必要な物を得ていました。 ただ、いつも欲しいものを相手が持っているとは限らないし、自分も、不要なものを常に用意できる訳ではありません。 そこで物品貨幣と呼ばれるものが誕生します。 価値があって、誰もが欲しがり、保存のきくもの。 布や米、塩などがお金の役目を果たしていました。 やがて人間が金属を生み出すようになると、刀などがそれに加わったといいます。
-

毎日届く情報誌 新聞の秘密
2015/02/24

日露戦争をきっかけに新聞業界は大きく拡大を見せます。 各社が競い合い、号外が1日に何度も発行されたとか。 明治30年代には、都市部だけでなく地方でも輪転機が普及したため、ぐんと発行部数が伸びました。 当時は勿論メールもありませんから、記事や写真を伝書鳩にくくりつけ「鳩便」で運搬していました。 新聞社の多い銀座・有楽町界隈では屋上でたくさんの鳩を飼っていたといいます。 新聞に欠かせない四コマ漫画についても触れてみましょう。 アメリカで19世紀に流行っていた風刺画を日本に持ちこんだのは今泉一瓢(いっぴょう)という漫画家。 風刺画ではなく漫画と名付けたのも、さらに四コマという形にしたのも彼なのです。
-

石板からはじまる新聞の歴史
2015/01/20

新聞の発生は世界の各地で確認されていますが、その中でも最初に新聞の原型をつくりはじめたのはユリウス・カエサル・ツェペリ(紀元前100-144)だとご存知でしょうか。歴史上に大きく名を残したカエサルですが、ローマの執政官となった際に、議会の議事録として「acta senatus(アクタ・セナトゥス )」と呼ばれる、板に書いた新聞を発行しています。 当時の議会ではきわめて不透明な政治が行われおり、カエサルは悩んでいたといいます。 そこで、一般市民を味方にするべく、新聞を貼り出す形で情報を公開していたのでしょう。
-

紙の宝石・蔵書票(後編)
2014/12/25

ここからは、すこし絵柄について触れてみたいと思います。 ヨーロッパで蔵書票が生まれてからしばらくは、宗教的な絵柄、特に天使や聖人、紋章などがほとんどでしたが、庶民に蔵書票が広がるのと同時にモチーフも多様化していきます。
-

紙の宝石・蔵書票(前編)
2014/11/11

蔵書票とは「エクスリブリス(EXLIBRIS)=誰それの蔵書から」という意味をもっています。 その名の通り"これは私の本だよ"という事を明らかにするために本に貼る紙片のこと。 その美しさから「紙の宝石」と呼ばれ、収集に夢中になるコレクターも多いのです。 今回はこの、紙の宝石・蔵書票について歴史をひも解いていきます。
-

文具からアートまで 進化をとげた付せんの魅力
2013/06/13

付せんとは、メモ書きを一時的に書籍や文書に張り付けるために使用される紙片――とあります。 この付せんの誕生は1968年アメリカ。 科学メーカー3Mの研究員スペンサー・シルバーは、強力な接着剤を開発中にもかかわらず、接着力がとても弱いものを作り出してしまいました。 そして、何につけてもくっつかない接着剤をみた同僚が「本のしおりにしてはどうだろう」と助言したことから、接着力の弱い接着剤の研究が始まったといいます。 約10年後の1977年には試作品が完成。 この試作品が大企業の秘書課に配られ、大好評を得て、1980年に全米で発売されることになりました。 「ポストイット」と命名されたこの付せん。 またたく間に世界に広がり、100ヵ国以上の国で販売されたそうです。
-

こだわりの自主制作誌“ZINE(ジン)”の広がり
2013/05/17

2010年代に入って日本でじわじわと、しかし着実に広がりを見せる紙文化のニューフェイスに“ZINE(ジン)”の存在が挙げられます。 ZINEは自分の好きなテーマで作る数十ページ程度の小冊子の総称で、部数は多くが100部未満。製法も原稿をコピーしてホッチキス留めするなど、手軽なものが主流です。 採算は度外視で、作り手は編集・執筆に関係のない本業を持つ人も少なくありません。 出版社や取次など既存の出版流通網を通さずに直接、書店や雑貨屋やカフェに置かれて読者の手に渡ります。
-

世界に一つだけの封筒 奥深い絵封筒の世界
2013/03/23

絵封筒とは封筒の宛名面を使って絵を描くアートのことです。 絵といっても水彩画のように描くものから、切り絵のように折り紙や布、リボンやテープなどを使ってコラージュするものまで、郵便物として発送できる範囲内で自由に表現することができます。
-

通販ダンボールの進化、常識やぶりの色柄と新たな用途
2013/01/12

皆さんは宅配された荷物を受け取った後、梱包に使われたダンボールをどうしているでしょうか。 多くの人は資源ごみなどとして出し、自治体の回収に協力していることと思います。 何しろ、ダンボールは回収率がここ数年、90%台の後半で推移。 回収されたダンボールは古紙として輸出されたり、ダンボールまたはほかの用途に再利用されたりとリサイクルが進められています。 しかし一方で、ごみ捨て場に持っていく前にもう一働きしてもらう、という人もいます。 今回は、梱包用ダンボールの再利用と、それを見越した企業の取り組みについて、お伝えします。
-

あえてアナログ こだわり年賀状
2012/12/01

年賀状の枚数は年々減少傾向にあるといいます。 日本郵政グループの発表によると、2012年1月1日に配達された年賀状は、前年比7.6%減の19億2500万通。 その背景には、インターネットの普及が考えられます。デジタルなEカードを年賀状として簡単に送ることができる時代です。 とはいうものの、年賀状の文化はしっかりと根付いており、年賀状がなくなるなんて考えにくいですね。 ある調査会社のアンケートよると、年賀状をハガキで送っている人は93.6%に対し、メールの人は42.1%。 その差は2倍以上です。
-

エコペーパー+αの時代
2012/10/01

よく耳にする「エコペーパー」とは、具体的にはどんな紙のことをいうのでしょうか? 「古紙の利用率が高いもの」「製造過程でCO2の排出量が少ないもの」「紙を漂白する工程で有害な化学物質を使っていないもの」等々、条件を挙げるだけでもきりがなく、その内容はまちまちのようです。 ここでは再生紙や、普段は捨てるもの(間伐材、廃材など)を使ったもの、紙を作る過程で環境に配慮しているものなど全てを、大きくとらえて「エコペーパー」と考えることにします。
-

思いを結び表現する水引
2012/07/11

水引とは、紙をひも状にした「こより」に糊を引いて乾かし固めたものをいいます。 結婚式のご祝儀袋を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。 ではその歴史は…と言えば、驚くことに飛鳥時代まで遡ります。 遣隋使・小野妹子が帰朝の際、海路の無事を祈願した隋からの贈り物に紅白の麻紐が結ばれていたことが発端だそうです。
-

業務用なのに「カワイイ」、ユーザーが育てたマスキングテープ
2012/06/29

製品の特定の箇所に、塗装などの加工を避けるために一時的に貼るマスキングテープ。 自動車の塗装や建築分野のシーリング、コーキング、エレクトロニクス分野のプリント基板上の回路保護などに使われる、れっきとした工業用品です。 ところが、この工業用品が今、アート好き女子などの間で人気を集めています。 いったい、マスキングテープのどんなところが人気を呼んでいるのでしょうか。 愛好家に話を聞いてみました。 開発者は3Mのエンジニア マスキングテープは1925年、米国で開発されました。 開発したのは、化学・電気材料メーカー、3M Companyの技術者だったRichard Gurley Drew氏。 ツートン・カラーの自動車の塗装工程において、2色の境界に貼って使うことを想定したものでした。 粘着力が弱く、剥がしやすいこと、剥がした後にのりが残らないこと、紙製のため手で簡単にちぎれること、作業用のメモなどを書き込めることなどが受け入れられ、さまざまな分野で使われるようになりました。
-

紙で人がつながるイベント マガジンライブラリー
2012/06/20

アート・デザイン系雑誌が世界各国から集まる雑誌の祭典 マガジンライブラリーは、ファッションやライフスタイル、インテリアといったアート系の雑誌・紙媒体を世界中から集める展示・紹介・販売イベントです。 雑誌をはじめとした多彩なプリントカルチャーとの出会いの場として有名で、雑誌やジン(インディーズ誌)、製品や作品を通じて新しい交流が生まれています。 企画・プロデュースは、アート・ディレクターの藤本やすし氏(CAP)とダヴィッド・グアリノ氏(A Zillion Ideas)。 2009年の初開催以来、国内外でさまざまなイベントへの参加招待を受けて回を重ね、これまでに延べ5万人以上が来場したといいます。
-

その歴史90年、ブックカバーという日本文化
2012/04/20

「日本の文化」と聞いて思い浮かべるものは何でしょう? 相撲、寿司、日本刀、盆栽、茶道。 あるいは、アニメやJ-POP、ゲームといったものでしょうか。 実は、こうした日本独自の文化の一つに、書店で本にかけてもらう「ブックカバー」も数えられます。 日頃、生活の中に溶け込んでいるブックカバー。使う人や提供する人はどんな意義を感じているのでしょうか。 広告メディアとしてのブックカバー ブックカバーの全国的な同好会である「書皮友好協会」によると、ブックカバーの歴史は大正時代までさかのぼることができるようです
-

人と人をつなぐ紙 レシートの新しい可能性
2012/04/18

台湾へ旅行にいった知人の話を聞いて驚きました。 なんと台湾のレシートは「くじ」になっているそうです。 スーパーで買い物をしてもらう細長いレシートは「統一發票」と言われ、8桁の数字が印刷してあります。 その番号が宝くじ(レシートくじ)になっているのです。 特等は200万元(約2600万円・2012.4現在)とか。 特等の下には1等20万元(約260万)から6等200元(約2600円)までが続きます。 買った物が少なくても、台湾のレシートは日本に比べて少し長め。 それもそのはず、裏面には、抽選日、換金場所、住所・氏名・電話番号の記入欄等、くじに対する注意書きが書かれているからだそうです。









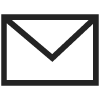 info@haguruma.co.jp
info@haguruma.co.jp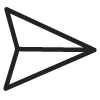 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム