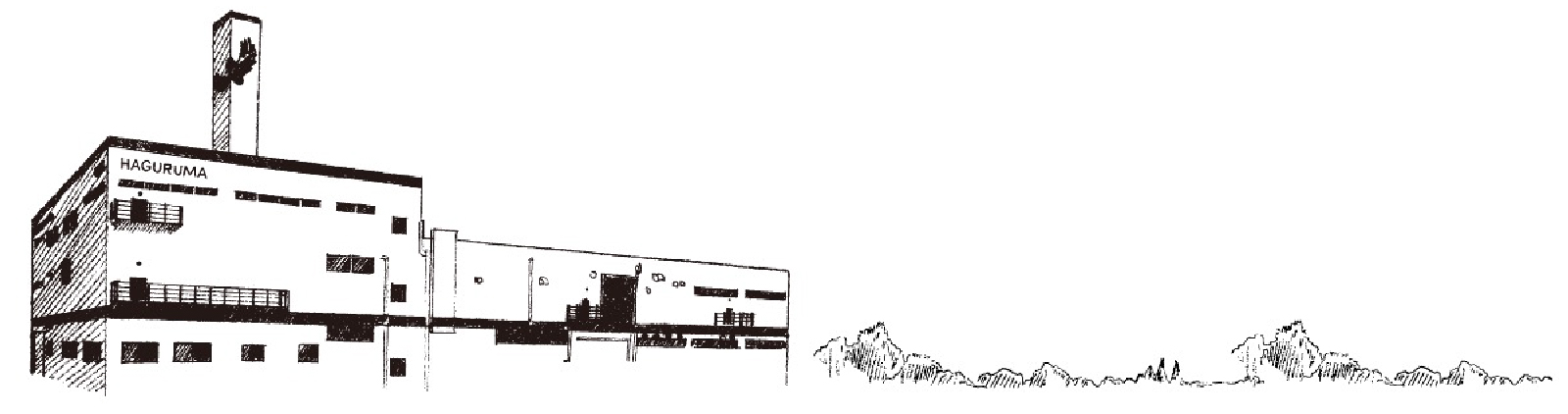マッチ箱 小箱に詰まった実用と図案 (中編)
2018/10/05
この頃は目にする機会がすっかりなくなったマッチですが、喫茶店などでレトロなデザインの箱を見かけると、その愛らしさに思わず手にとってしまいます。 多くのデザイナーに影響を与えたというマッチ箱の図案。中編ではラベルデザインと印刷に注目したいと思います。

デザインの側面からも、マッチの魅力について紹介していきましょう。
神戸港からはじめてマッチが輸出されたのは明治11年のこと。
その後、日本の重要な輸出商品の一つとなっていくわけですが、当時は図案にまつわるトラブルが絶えませんでした。
というのも、評判のいいマッチがあると知ると、それを堂々と真似て、社名だけを書き換えて販売するという事件が多発。
しかし、その元ネタをデザインした側も、海外のマッチをそっくり真似していたりと、手のつけられない状況だったそうです。
そこで政府が制定したのが、マッチラベルの商標登録。
この制度が整う事で、類似デザインを防ぐという目的のほかにも、品質を見分ける事が出来るという利点もありました。
また、海外にウケのよいラベルを輸出向けにデザインし商標化したところ、評判は上々。
マッチの輸出ビジネスは順調に発展を遂げていきます。ピーク時には、国内生産量の8割が海外へ輸出されていったと言います。

画像上:復刻された輸出マッチ。モチーフが愛らしい。
海外で好まれるデザインと一概に言っても、文化や慣習に合わせた図案であることが求められていました。
例えば中国では、龍や猿、桃。インドは象、クジャク、神。上海は虎。オーストラリアではカンガルーといったモチーフが人気。
それらを形にしていくのが、今でいうイラストレーターである「画工」の仕事です。
ちなみに当時のマッチ画工は、浮世絵師や絵馬師からの転職組が多かったとか。需要が大きく、羽振りも良かったのかもしれませんね。

画像上:木口木版はこのようにして作られる。
さて、マッチの印刷はどのように行われていたのでしょうか。初期の頃は、木版や銅版の単純なもので、印刷の精度も粗悪だったようですが、
需要も増え、それだけでは済まなくなってきます。
ひとつの節目となるのは明治20年。木版画家の合田清が、木口木版(こぐちもくはん)の技術をフランスで学び、帰国します。
木口木版とは、年輪が締まって堅いつげや椿などの樹を輪切りにした彫刻法で、日本のそれよりも精密で繊細な表現が可能になります。
合田は「生巧館」という木口木版工房を開設、多くの職人に板づくりを伝授していきました。
版ができたら複製していきます。この頃に重宝されていたのが、木版に鉛を塗りミツロウで型取りし、電気分解を利用して製本する「電気版」と呼ばれる方法。
その後、石版の多色刷りへ、そして昭和のオフセット印刷へと、マッチの印刷方法も時代とともに移り変わり、より美しく精度の高い作品のようなマッチが生まれていきます。
後編では、コレクターからの人気も高い、広告マッチについて紹介していきます。(続く)
文・峰典子
--------------------------------------------------
参考文献:
「絵画の教科書」日本文教出版
「マッチラベル パラダイム―燐票商標様式美」木耳社
「世界大百科事典 第2版」平凡社
関連記事
マッチ箱 小箱に詰まった実用と図案 (前編) >









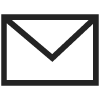 info@haguruma.co.jp
info@haguruma.co.jp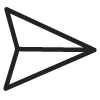 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム