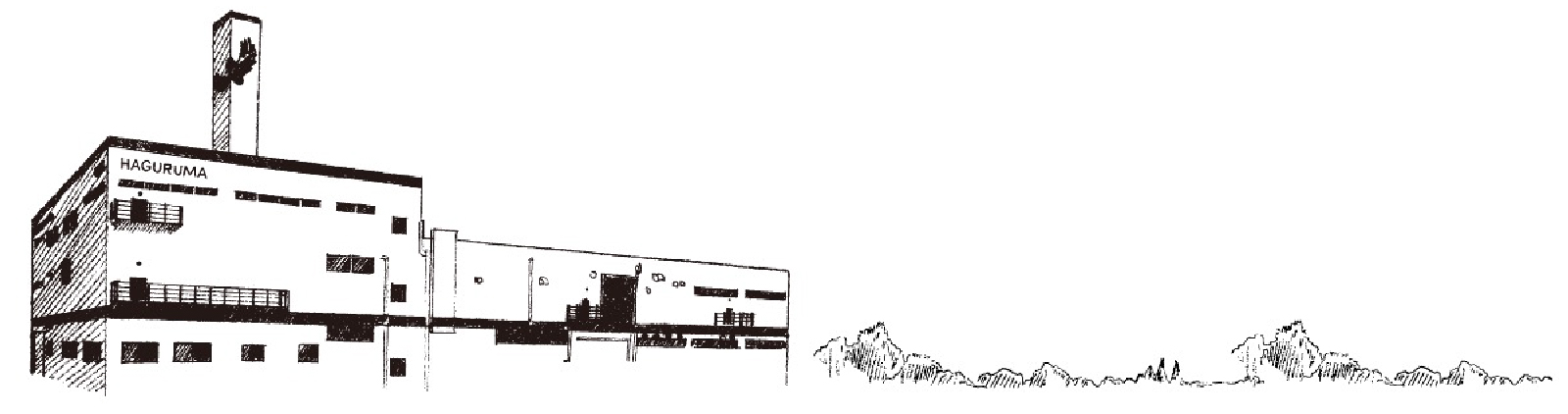奥ゆかしい日本の伝統 ふすまの歴史 (後編)
2016/03/30
平安時代に生まれた、日本オリジナルの建具「ふすま」。
親しみのあるものですが、かえって知らないことも多いようです。
二回に渡り、奥深いふすまの魅力に迫ります!

呼吸するふすまで温度調整
貴族のものであったふすまですが、江戸時代後期には、紙の生産技術が向上するのと共に、庶民の家でも普及していきます。
明治21年に建てられた皇居新宮殿は、和洋折衷を大きく打ち出したもので、人々の住宅に対する意識を大きく変化させるきっかけとなりました。
それ以降、洋室と和室を襖で区切るという、いわゆる“昭和の住宅”が日本中で建設されていきます。
構造そのものは、平安時代から現在まで、ほぼ変わらないふすま。
保湿や防音にも優れているのはもちろん、温度調整の機能まで備わっています。
そもそも和紙は呼吸しているため、湿度を整える作用があるのです。
季節によって気温の変化が激しく、湿度も高い日本ですから、その良さを見直したのではないでしょうか。
多種多彩なふすま紙
ふすまに興味を持ってくださった方のために、ふすま紙についてもぜひ紹介させてください。
ふすま紙は、「鳥の子紙」と「織物」の2つに分けることができます。
鳥の子とは雁皮(がんぴ)からつくる和紙の一種で、その名の通り、卵のような淡い黄色をしているもの。
現在では、手漉きと機械漉きをわけるため、手漉き紙を「本鳥の子」、そして機械で漉ったものを「鳥の子」と呼びわけています。
さらに、雁皮の配合率や、漉き込み模様をつけたものなど、鳥の子紙だけとってみても、種類は豊富。
ちなみに、「本鳥の子」は、現在ほとんど作られていないため、とっても高価なのだとか。
一方、織物には、合成繊維を用いた一般家庭用のものと、麻や絹、木綿などの天然素材を織ったものがあります。
これら以外にも、唐紙(木の版で柄をつけたもの)や、銀箔で色をつけたものなど、そのバリエーションの多さに驚かされます。
デザインと機能重視の現代ふすまで「しつらう」
とにかく狭いといわれる日本の住宅で、小スペース化を図れるふすま。
最近は、より柔軟な発想のものが増えてきました。
洋室にも溶け込むよう、表と裏でデザインを変化させたものや、ガラスでできた透明なふすま、耐久性のつよい紙でつくられたもの。
ふすまは、わたしたちの暮らしに合わせて調和していく建具なのです。
行事や季節に合わせ、ふすまで部屋を仕切って暮らしていた平安時代。
人々はこの設営のことを「しつらい」と呼んでいました。
ふすまは、単純な間仕切りとしての役割だけでなく、生活や日本の風土を色濃く反映したものだったことが分かります。
かつて、建築家のブルーノ・タウトがふすまについて書き残した一文を最後に紹介します。
「実際、これ以上単純で、しかも同時にこれ以上優雅であることは、まったく不可能である」
<タウト「永遠なるもの」『日本の家屋と生活』所収、篠田英雄訳、岩波書店>

画像上:ルノン株式会社 古紙を85%使用した襖紙「凜」
文・峰典子
--------------------------------------------------
参考:
「住まい学大全081 ふすま」向井一太郎・向井周太郎 著
(住まいの図書館出版局)
関連記事
間仕切りから芸術へ ふすまの歴史 (前編) >









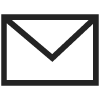 info@haguruma.co.jp
info@haguruma.co.jp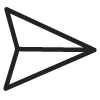 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム