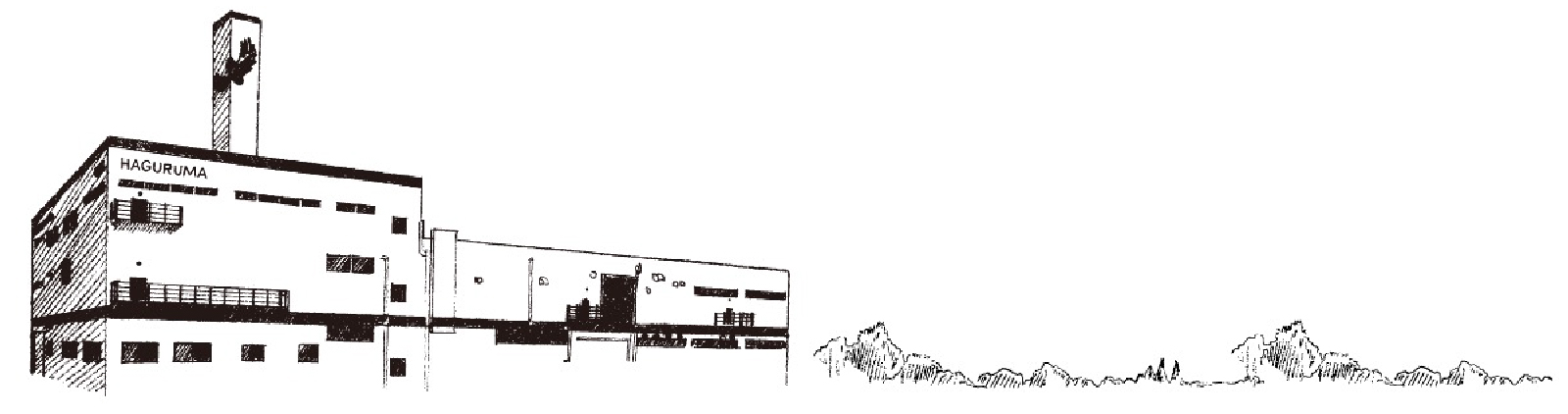喪中ハガキも個性の時代!?
2011/10/06
昔から「喪中ハガキ」はシンプルな白いカードに厳かな文章というイメージがありますが、最近では亡くなられた方を思う気持ちと年賀状を失礼するアナウンスとして少しシンプルでありながらも美しいデザインやオリジナルのメッセージを入れたものも多くなってきました。喪中ハガキの今と昔、これからを考えてみます。

今年六月に祖父が永眠致しましたため
新年のご挨拶を申し上げるべきところ
喪中につきご遠慮申し上げます
このような文章がプリントされたハガキを小学生の冬、同級生から受け取った覚えがあります。
小学生のころはクラスメートと毎日顔を合わせていて、手紙のやりとりは年賀状くらい。
その内容といったら「おモチを食べすぎないようにね!」などというレベルのものでした。
初めて格式ばったハガキを受け取って、当時は面食らったものです。
いま思うと、喪中ハガキというのはそれくらい、出す人や受け取る人が誰であれ、決まった形を踏襲するのが当たり前だったのだなと感じます。
悲しいばかりが喪中ハガキじゃない
時は移り、最近では、この喪中ハガキ(年賀欠礼状)も、徐々に多様化する傾向にあるようです。
東京・大阪に店舗を構える手紙用品店ウイングド・ウィールによれば、例えば、年賀欠礼状を、ハガキではなく封書で送る人が増えてきているといいます。
年賀欠礼状は、年賀のあいさつができないことを詫びるものですが、日頃の付き合いによっては、受け取った人がその欠礼状で初めて悲報に接することもありえます。
いきなり文面が目に入るハガキよりも、封筒に入ったカードにしたほうが、受け取る人にとってありがたい場合もあるのかもしれません。

封書にして送る喪中ハガキも増えつつある
文面については、従来通りの定型文に倣う人がほとんどだといいますが、中には、故人の手書きメッセージを、その文字ごと取り入れたケースもあるそうです。
見た目も、一般的には明るい印象にならないよう、無地のカードに文字色がダークグレイなど、色数が少なく控えめなデザインが選ばれますが、最近では、故人らしさをどこかにワンポイント取り入れる例がちらほら見られるようになりました。
例えば、故人が愛用していた身近な品(眼鏡や帽子など)をマークとしてあしらったケースもあるそうです。
ハガキ専門サイト「ハガキSTORE」のデザイン例にも、お酒好きだった故人をしのぶ意図で、徳利とお猪口のイラストを入れたものが掲載されています。
文面やデザインにオリジナルの要素を入れる人には、例えば「故人が明るい人だったから、喪中ハガキも明るく」など、故人の個性を大切にしたいという思いがあるようです。

マナーも諸説、大切なのは気持ち
文面やデザインに広がりが出てきた喪中ハガキですが、そのマナーや作法についても、捉え方にずいぶん幅が出てきているようです。
服喪中に新年を迎える場合に、年賀状のやりとりをしてきた相手へ、12月上旬までに届ける(その際は誰が亡くなったか明記する)という骨格には変わりがありませんが、いくつか、専門家によって正反対の見解が示される部分もあります。
考え方がまちまちなのは、例えば、喪中ハガキを親族にも送るべきかどうかという点。
冠婚葬祭のマナーを紹介するWebサイトの中には、《親族は当然、喪中であることを知っているので、ハガキを出す必要はない》としているところもあります。
一方で、《喪中ハガキは、あくまで新年のあいさつができない非礼を詫びるものであって、亡くなったことを知らせる目的で出すわけではないので、親族にも礼儀として出すべき》とするサイトも。
専門家の間でも意見の分かれるところのようです。
また、受け取る側の対応として、喪中ハガキを受け取る前に年賀状を出してしまったときの処し方も、人によって考え方が異なります。
一説には、《松の内が明けてから「寒中見舞い」や「お悔やみ状」を送り、一言謝罪するべき》とされています。
しかし、過去、大手新聞のマナー解説欄に「それはしかたのないこと。謝る必要はない」と明記されたこともあり、どうやら、これが絶対といえるような対応はなさそうです。
そもそも、どういう続柄の人が亡くなると、どれだけの期間、喪に服すべきなのか、というところからして、誰もが認める決まりというのは存在しません(明治時代には太政官布告が出されましたが、夫が亡くなると服喪期間は13カ月、妻が亡くなると90日などと定められていて、現代の感覚には到底そぐわないと思われます)。
喪中ハガキのこれから
世界保健機関の調べによれば、2011年の世界各国の平均寿命で、日本は世界首位(83歳)に立ちました。
今後ますます高齢化が進むといわれる日本。
私たちの家族観や死生観、生活習慣が変化するにつれて、喪中ハガキの送り方や存在そのものも、ゆるやかに変わっていくのかもしれません。
例えば、長生きして大往生を果たした人のことは、その人生や功績を称えて明るく送り出すのも、遺族の心が許すのであれば、失礼や非常識には当たらない気がします。
一方、かの夏目漱石は、『吾輩は猫である』のモデルになった黒猫が死んだとき、親しい人たちに猫の死を知らせる手紙を書き送ったそうです。
彼の友人は彼を非常識だと笑ったでしょうか。
私にはそうは思えません。
大切なのは、いろいろと意見の分かれるマナーを検証することではなく、あくまで、故人を悼む気持ちと、それによって礼を欠くことになる相手に詫びる気持ち。これがこめられていれば、多少のことで目くじらを立てる人も少ないのではないでしょうか。
毎年続いてきた年賀状が途切れると、事情を知らない人は寂しい思いをします。
秋も深まってきたら、喪中の方は、自分にとっての年賀欠礼状のあり方を一度考えてみてもいいのかもしれません。
羽車企画広報部編集









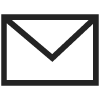 info@haguruma.co.jp
info@haguruma.co.jp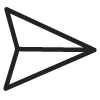 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム